私は低山登山を始めて1年で約30回ほど山を登りました。その中で、初心者がやりがちなミスをほとんど経験してきたと思います。この記事では、そんな私の失敗談を紹介し、同じミスをしないための対策をお伝えします。
1. ペース配分を誤るとツラいだけの登山に…
初めての登山では、自分の体力や脚力が分からず、どのペースで登ればいいのか判断が難しいものです。また、「登山は体力勝負」という意識があると、多少息が上がっても無理をしてしまいがちです。
私も最初の登山では、周囲の景色を楽しむ余裕もなく、ただただ辛い経験になってしまいました。
対策:
- こまめに休憩を取る(無理に進まず、少しずつ体を慣らす)
- 一定のペースを意識する(最初は「少し遅いかな?」と思うくらいがちょうど良い)
- 登ることを目的にせず、景色を楽しみながら歩く
登山は「頑張るもの」ではなく、「楽しむもの」。無理せず、余裕を持って登りましょう。
2. 登山中の水分管理、失敗するとツラい…
低山は標高が低いため、特に真夏は気温が高くなりやすく、ついつい水分を多く摂ってしまいます。水分補給は大切ですが、一度に大量に飲むとお腹がタプタプになってしまい、動きにくくなることも。
また、登りで水をたくさん飲みすぎてしまい、下山時に水が足りなくなるという失敗もしました。
対策:
- 少量ずつ、こまめに水分補給する(一気飲みはNG)
- 水の消費量を考えてペース配分する(登りで飲みすぎない)
- 予備の水を持つ or 行動食に塩分補給を意識する(発汗量が多い時に対応)
3. 天気を甘く見て痛い目に遭う
「山の天気は変わりやすい」とよく言われますが、低山でも同じです。私は「天気予報では晴れだから大丈夫」と思い、レインウェアを持たずに登ったことがありました。しかし、突然の強い雨に打たれ、服がびしょ濡れになり体が冷えてしまう危険な状況に。
対策:
- 必ずレインウェアを持っていく(晴れ予報でも備えは必須)
- 天気の急変に備えた装備を準備する(防寒着、タオルなども持参)
- 登山前に天気予報を確認し、天候のリスクを考える
登山中に雨に降られると、体温低下や滑落のリスクも高まります。油断せず、しっかり準備しましょう。
登山では天候の変化をしっかり確認することが重要です。特に GPV気象予報 を活用すると、登山エリアの 細かい気象状況 を事前に把握できます。
🌤 GPV気象予報をチェックする 👉 GPV天気予報
GPVのポイント:
- 数時間ごとの詳細な天気予報が見られる
- 降水量・風速・気温などをピンポイントで確認可能
- 登山計画のリスク回避に役立つ
登山前に天気をしっかりチェックして、安全な登山を楽しみましょう!
4. 標高だけで判断すると危険!
私は300m程度の低山に10回ほど登った後、「そろそろ1000mの山にも挑戦できるだろう」と考えました。しかし、実際に登ってみると、登りにくいガレ場(崩れやすい岩場)が多く、途中で引き返すことに。標高だけでなく、登山道の状況も重要だと痛感しました。
対策:
- 最初は300~600m程度の山から慣れる
- 標高だけでなく、登山道の難易度やルート情報を調べる
- 「なんとかなるだろう」という過信をしない(無理な挑戦はしない)
特に、初心者は歩きやすい道がある山を選ぶのが大切です。
5. 日没リスクを甘く見た結果…
登山を続けるうちに、「少し遅い時間からでも登れるだろう」と思うようになりました。ある日、別の用事があり、予定より遅れて登山開始。秋だったため日暮れが早く、下山時にはすでに暗くなり、道が見えづらくなってしまいました。
対策:
- 日没時間を確認し、余裕を持って計画を立てる
- 遅い時間になったら登山は諦める(無理は禁物)
- ヘッドライトを持参する(万が一、暗くなっても安心)
低山でも、日没後はかなり暗くなります。計画的に行動しましょう。
時間に追われて山に登ることは危険です。詳しくはこちらの記事もご覧ください。
さいごに
ここでは、私が実際に経験した低山登山の失敗談を紹介しました。今後も登山を続けていく中で、新たな失敗があれば追記していこうと思います。
登山は楽しいですが、ミスをすると危険も伴います。この記事が、これから低山登山を始める方の参考になれば幸いです。安全で楽しい登山を心がけましょう!


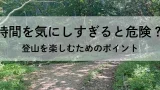
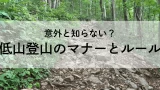


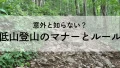
コメント